iPhoneのデータ移行時に、特に移行手続きは必要ありませんでした。新端末でもそのまま楽天銀行アプリにログインできました。
念のため、楽天IDとログインパスワード、楽天銀行の口座番号などを確認しておくといいと思います。
Q&Aはこちら↓
スマートフォンの機種変更 - 楽天銀行
https://www.rakuten-bank.co.jp/guide/mobile/change.html
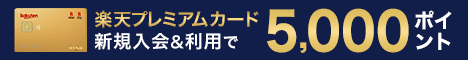
iPhoneのデータ移行時に、特に移行手続きは必要ありませんでした。新端末でもそのまま楽天銀行アプリにログインできました。
念のため、楽天IDとログインパスワード、楽天銀行の口座番号などを確認しておくといいと思います。
Q&Aはこちら↓
スマートフォンの機種変更 - 楽天銀行
https://www.rakuten-bank.co.jp/guide/mobile/change.html
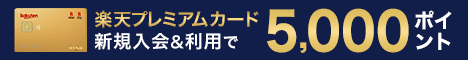
iPhoneのデータ移行後、特に手続きはいりませんでした。新端末でそのままアプリにログインできました。
うまくいかなかった場合はQ&Aをチェックしてください。
スマートフォンの機種変更をした場合、ゆうちょ手続きアプリを引き継ぐことはできますか。
https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?id=10892

以下はiPhoneの新端末と旧端末が両方ある前提での以降手順です。
・必要なもの
・口座番号(またはID)、パスワード
・移行手順
1.旧端末でSMBCセーフティパスを解除する。
「メニュー」>「セキュリティ設定」>「解除」を選択。
2.新端末でアプリを立ち上げ、口座番号とパスワードでログイン。
3.セーフティパス設定と同意画面が出てくるので同意する。
4.生体認証が求められるので生体認証する。
5.SMS認証か、本人確認書類の読み取り。
SMS認証が簡単なのでそちらにしました。新端末のSMSの認証コードを入力。オレンジの登録を押して完了。


↓旧端末がもう手元にない場合の手続
SMBCセーフティパス機種変更後の設定方法 - 三井住友銀行
https://www.smbc.co.jp/kojin/direct/securi/safetypass/kishuhenko
以下はiPhoneの新機種へのデータ移行が完了した後の話です。三菱UFJダイレクトのワンタイムパスワード設定済みの状態です。
・必要なもの
・店番号、口座番号(または契約番号)、ログインパスワード、運転免許証またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
・移行手順
1.新機種でUFJ銀行のアプリを起動する。口座番号(または契約番号)とパスワードでログイン。※そのままでも使えますが、本人確認をしないと1日の限度額が10万円に制限されます。
2.本人確認手続。運転免許証またはマイナンバーカードを新端末のスマホに読み取らせます。
自分はマイナンバーカードを使いました。
マイナンバーカードと4桁のセキュリティコード入力を求められます。セキュリティコードはカードの左下に書いてあります。
3.顔認証手続。顔の自撮りとまばたき画像を求められます。まばたき画像がなかなか成功しませんでした。
4.ワンタイムパスワードの設定。
5.生体認証の再登録。
機種変更されたお客さまへ - 三菱UFJ銀行
https://direct.bk.mufg.jp/btm/banking/sp_change.html


iPhoneの機種変更したので、その時の手順をメモしておきます。
以下はiPhoneの新機種へのデータ移行が完了した場合の話です。
・必要なもの
・店番号、口座番号、ログインパスワード
・移行手順
1.新機種でPaypay銀行のアプリを起動する。「パターン再登録」をタップ。(※ここで旧機種で登録済みのパターンを入力してもログインできません。)
2.店番号、口座番号、ログインパスワードを入力する。
3.パターンの再設定をする。(※以前と同じパターンでも大丈夫でした。)
4.生体認証したい場合は生体認証の設定をする。
以上です。
機種変更後のアプリの再登録方法 - Paypay銀行
https://www.paypay-bank.co.jp/support/modelchange.html
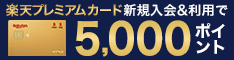


iPhoneを機種変更した時に住信SBIネット銀行の移行作業に手こずったのでメモしておきます。
新機種の端末に移行した後、住信SBIネット銀行のアプリを立ち上げる→スマート認証NEOの手続を求められる→失敗してアプリ落ちる、というトラブルに見舞われて上手くいかない、公式サイト見てもよくわからなかったのですが、2日かけてなんとか解決したので手順を書いておきます。
・必要なもの
・ユーザーIDとログインパスワード(Safariなどのブラウザでログインできるか確認してみてください)
・SMS受信できる設定の新端末
以下はiPhoneの新機種にSIMを入れて移行した後の話です。
・移行手順
1.旧端末のアプリを起動し、「ログイン承認機能」をOFFにする
「アプリ設定」>「ログイン承認機能を利用する」のスイッチをOFFに
2.旧端末のアプリ内で「ログアウト」する。
「メニュー」>「ログアウト」を選択。(※ログアウト前にユーザーIDとログインパスワードの確認を忘れないように)
3.新端末のアプリを起動し、ユーザーIDとログインパスワードを入れてログインする。
4.「スマート認証NEOを利用する」を選ぶ。SMS認証が求められるので、新端末の電話番号に来たSMSの番号を入力。
5.新端末のスマート認証NEOの再登録完了。
旧端末のログアウトをしないと、いくらやっても新端末でエラーになります。公式のQ&Aには1は書いていても、2は書いていなかったので気づくのに2日かかりました。
いったんログアウトするので、ユーザーIDとログインパスワードが必要になります。わからない場合は、旧端末で確認か、変更の手続をとってください。SMS認証が必要だったらSIMを旧端末に戻すといいでしょう。
この記事を読んで役に立ったという人は右下の楽天かヤフーまたはAmazonのアイコンをクリックして電池かスマホカバーでも買って行ってください。
「このまま預金引き出せなかったらどうしよう……」と無駄に悩んで眠れなかった日々(2日間)が多少は報われると思います。



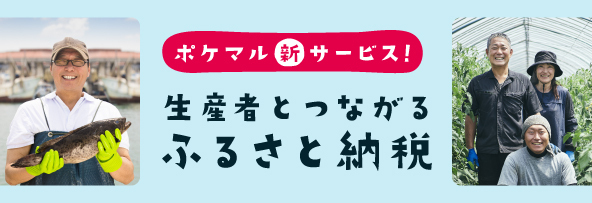
スマートフォン機種変更時の注意点について-住信SBIネット銀行
電話番号も変更した場合は↓
◯遠交近攻【えんこうきんこう】 (漢検4級相当)
◎意味 遠い国と国交を結んで、近くの国を攻撃すること。孫子の兵法三十六計の第二十三計。
「遠きと交わり近きを攻む」と訓読することもある。
◎故事
秦の昭襄王(始皇帝の三代前の秦王)が宰相の范雎(はんしょ)の助言により、それまで秦の隣国の韓と魏と同盟して、斉を攻めていたのをやめさせて、逆に斉と同盟して、韓と魏を攻めるようになった。遠くの国と同盟することで近くの国を挟み撃ちの形で有利な形で攻めることができる。外交戦略のひとつ。
◎歴史上の実例
・第一次世界大戦(1914-1918)時の三国協商。勢いを増してきたドイツを抑えるため、西側のイギリス・フランスと東側のロシアが同盟を結んだ。これに対してドイツはオーストリア・トルコと三国同盟を結んで対抗し、西のフランス、東のロシアと同時に戦う二正面作戦を強いられた。
・日英同盟(1902-1923) 中国大陸に進出したい日本とロシアの勢力拡大を阻止したいイギリスの思惑が合致して日英同盟が結ばれた。その後の日露戦争(1904)で日本がロシアに勝利するきっかけとなった。
・濃越同盟 元亀三年(1572)美濃の織田信長と越後の上杉謙信との間の同盟。不和になった将軍足利義昭が甲斐の武田信玄、近江の浅井長政、越前の朝倉義景、摂津の本願寺に信長打倒を呼びかけて信長包囲網を形成したので、武田信玄を牽制するため、上杉謙信と同盟して、武田軍の西進に備えた。
「喜連川」
この地名が読める人は地元民かよほど関東の地理や戦国武将に詳しい人だろう。
喜連川―現在は栃木県さくら市―江戸時代にこの名を聞いた人はどことなく高貴な感触を持ったことだろう。それもそのはず下野国の喜連川藩の藩主は「御所さま」「公方さま」と呼ばれていたからだ。
御所とは京都御所のように帝のおわす所、大御所のように引退した征夷大将軍とくに徳川幕府初代将軍である神君家康公のことを憚って呼ぶ名称である。公方とはこれまた将軍のことを指す尊称である。
かくも尊く呼ばれる喜連川藩はさぞや大藩なのかと思いきや、石高はわずか五千石。
1石が1000合だから1日3合食べるとすると1石は約1年分の米ということになる。収穫した米をそのまま藩内で消費していたとしたら喜連川藩はたった5000人の人口の町でしかなかったことになる。金銭に換算すると1石=金1両が江戸初期のレートで、ざっくり現在の貨幣に換算すると1両=10万円程度らしいので、5000石は約5億円に相当する。個人事業主なら左うちわで笑いが止まらないだろうが、この予算で市町村を運営するのは非常に厳しい。参考までに2025年の日本国内の人口5000人の町、北海道の上士幌町の年間予算は99億円。十勝毎日新聞
さて江戸幕府の法制度に詳しい方なら首をひねったことだろう。五千石では藩主と言えぬ。大名と名乗るには一万石以上必要で、それ未満は小名というか旗本なのではないか。検地の役人が間違えたか、転封や減封を食らって一万石以下に落とされてしまったのか。
その辺の事情は本書を読んでもらうとして、五千石という貧乏な小藩がいったいどうやって藩政を経済的にやりくりしていたのか、その秘密に迫るものである。
近世とはいえ江戸時代は士農工商の身分制度であったから、武士階級まして大名であれば何かと名目をつけて御用商人から徴発したり、いざとなれば借金を踏み倒すという裏技を使って楽勝だったのではと思うだろう。歴史上最も有名で規模が大きい踏み倒しは幕末の薩摩藩の五百万両だろう。薩摩藩の家老調所広郷は商人を一同に集め、借金500万両を無利子で毎年2万円ずつ250年かけて返すと宣言し、これが飲めないなら腹を切ると脅迫し、商人たちに強制的に承諾させた。もちろんこの図々しい踏み倒し契約(返さないとは言ってないが無利子なら贈与と同じ)は最後まで履行されたわけがなく明治になって薩摩藩も消えてうやむやになってしまった。
しかし、われらが誇り高き喜連川藩はそんな小狡い手段には頼らない。おもてなしの精神を発揮し、大大名からも一目置かれ、領民の暮らしに日々心を砕き、領内の巡察を欠かさない。きわめて珍しいことに喜連川藩領内では江戸時代の約260年間一度も一揆が起きていないのである。それだけ領民から慕われていたのだろうとうかがわれる。
喜連川藩主のやりくりの苦労を知ると、現代の地方自治体がふるさと納税のあれやこれやで財源の確保に心を悩ませているのと通じるものがある。
歴史をすでに終わった遠い過去の話ととらえるのでなく、現代とも通ずる人類普遍の事柄ととらえることで、歴史的建造物やゆかりの土地が活き活きと見えてくる。護美錦と名高いサツキの花、手入れの負担を考えた鼈甲垣も風情あり、十代藩主が領民のために整備した御用堀の水路に今も水が流れていることを実見できるだろう。
本書は文庫本としては200ページ未満と短めだが、これだけの内容を要領よくまとめるには相当な史料の分析とバックグラウンドが必要と思われる。
現代の喜連川はどうなっているのか興味がわいた人は実際に見に行ってみるといい。東京駅から新幹線利用で1時間30分ほど。
さくら市 喜連川散策マップ
https://sakura-navi.net/tourism-speciality/tour-guide-map/kitsuregawa-map/
日本三大美肌の湯といわれる喜連川温泉で疲れを癒やしていってもいいかもしれない。
