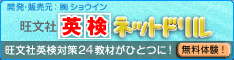【原文・歴史的仮名遣い】
春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山
持統天皇
【ひらがな表記・現代仮名遣い】
はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすちょう あまのかぐやま
【現代語訳】
春が過ぎて、いつのまにか夏が来たらしい。夏に白い衣を干す天香久山のほとりに、あのように真っ白い衣が点々と干してあるよ。
【文法・修辞】
●「春過ぎて 夏来にけらし」で二句切れ。
●「けらし」は、「けるらし」の「る」が脱落したもの。過去の助動詞「けり」の連体形と推定の助動詞「らし」の終止形。
●「白妙の」は衣や雪など白いものに係る枕詞。
●「てふ」は「といふ」が縮まった形。伝聞。
【作者・背景】
●持統天皇(645~702)
女帝。第42代天皇。天智天皇の第二皇女で、天武天皇の皇后となり、天武天皇の死後、持統天皇として即位。藤原京に遷都した。政治面では藤原不比等らに命じて大宝律令を編纂させるなどした。『万葉集』に持統天皇の歌は長歌2首と短歌4首が収められている。長歌2首と短歌2首は天武天皇の死の悲しみを歌った作品である。
●『新古今集』夏・175収録。
『万葉集』巻一の「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣ほしたり天の香具山」が原歌。素朴で直接的な表現の『万葉集』に比べ、『新古今集』では、「夏来にけらし」「衣ほすてふ」と伝聞表現でより観念的になっている。『新古今集』の成立した1200年頃には、7・8世紀の『万葉集』の夏に衣を干す習俗は廃れていたのか、それとも新古今集の編者の好みで伝聞表現を選択したかもしれない。
●天の香具山
標高152メートル。大和三山(香具山・畝傍山・耳成山)のひとつ。奈良県橿原市にある。